WW2後の中国ではM3リー/グラント中戦車はどうなったか?
 どうも、皆さん。タンコスキーという者です。よろしくお願いします。
どうも、皆さん。タンコスキーという者です。よろしくお願いします。
WW2時の中国軍が使用していた戦車のその後等を調べていたのですが・・・
中国語版のWikipediaにて
M3リー/グラント中戦車が国府軍にて使用されていた。
との、記述があったのですが・・・その場合、国共内戦にて使用された可能性はありますでしょうか?
そもそも本当に、M3リー/グラント中戦車は国府軍にて使用されていたのでしょうか?自分ができる範囲で色々調べたのですがそれらしい記述が見つからなくて・・・
Re: WW2後の中国ではM3リー/グラント中戦車はどうなっ
 第2次大戦終結後に、日本軍との戦闘で疲弊して弱体化していた国民党軍を支援するために、アメリカがM4中戦車を供与した事実は判明していますが、M3中戦車が供与されたかどうかについてはよく分かりませんね。
第2次大戦終結後に、日本軍との戦闘で疲弊して弱体化していた国民党軍を支援するために、アメリカがM4中戦車を供与した事実は判明していますが、M3中戦車が供与されたかどうかについてはよく分かりませんね。
手持ちの資料を幾つか見てみましたが、それらしい記述は見つかりませんでした。
まぁ、M3中戦車は当時すでに旧式化していてアメリカ軍では不要な存在になっていたので、国民党軍に供与されたとしても不思議は無いですね。
中国語版Wikipediaの記述は、ある程度信用できるのではないかと思います。
 コンバット猫丸
コンバット猫丸  2024/12/20(Fri) 19:49 No.300
2024/12/20(Fri) 19:49 No.300
 第2次大戦終結後に、日本軍との戦闘で疲弊して弱体化していた国民党軍を支援するために、アメリカがM4中戦車を供与した事実は判明していますが、M3中戦車が供与されたかどうかについてはよく分かりませんね。
第2次大戦終結後に、日本軍との戦闘で疲弊して弱体化していた国民党軍を支援するために、アメリカがM4中戦車を供与した事実は判明していますが、M3中戦車が供与されたかどうかについてはよく分かりませんね。手持ちの資料を幾つか見てみましたが、それらしい記述は見つかりませんでした。
まぁ、M3中戦車は当時すでに旧式化していてアメリカ軍では不要な存在になっていたので、国民党軍に供与されたとしても不思議は無いですね。
中国語版Wikipediaの記述は、ある程度信用できるのではないかと思います。
 コンバット猫丸
コンバット猫丸  2024/12/20(Fri) 19:49 No.300
2024/12/20(Fri) 19:49 No.300
無題
 どうも、コンバット猫丸さん。返答、ありがとうございます。タンコスキーです。毎回とても助かっています・・・
どうも、コンバット猫丸さん。返答、ありがとうございます。タンコスキーです。毎回とても助かっています・・・
>国民党軍を支援するために、アメリカがM4中戦車を供与した
>国民党軍に供与されたとしても不思議は無いですね
M4A4シャーマンがイギリス軍経由?で国府軍にて使用されていて人民解放軍でも一時期使用していたのは調べていた時に知ったので「もしかしてM3中戦車はどうなのだろう?」と、感じた疑問が解消できそうです
コンバット猫丸さん。ありがとうございます・・・
 タンコスキー
タンコスキー  2024/12/20(Fri) 21:12 No.301
2024/12/20(Fri) 21:12 No.301
 どうも、コンバット猫丸さん。返答、ありがとうございます。タンコスキーです。毎回とても助かっています・・・
どうも、コンバット猫丸さん。返答、ありがとうございます。タンコスキーです。毎回とても助かっています・・・>国民党軍を支援するために、アメリカがM4中戦車を供与した
>国民党軍に供与されたとしても不思議は無いですね
M4A4シャーマンがイギリス軍経由?で国府軍にて使用されていて人民解放軍でも一時期使用していたのは調べていた時に知ったので「もしかしてM3中戦車はどうなのだろう?」と、感じた疑問が解消できそうです
コンバット猫丸さん。ありがとうございます・・・
 タンコスキー
タンコスキー  2024/12/20(Fri) 21:12 No.301
2024/12/20(Fri) 21:12 No.301
米国テキストロン製のT-6に決定
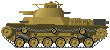 国産じゃなくなる!? 空自の新たな「初等練習機」が決定! スバル脱落で勝ったのは?
国産じゃなくなる!? 空自の新たな「初等練習機」が決定! スバル脱落で勝ったのは?
https://trafficnews.jp/post/136489
空自の次期初等練習機がT-6に決定したようです。時期高等練習機にT-7Aを導入する為の物なんでしょうね。
Re: 米国テキストロン製のT-6に決定
 航空自衛隊の初等練習機はこれまでT-3、T-7と2世代に渡ってスバル(旧・富士重工業)製の機体が採用されてきましたが、今回スバルは機体の開発には参加せず、スイス製のPC-7MKXのライセンス生産を提案していたんですね。
航空自衛隊の初等練習機はこれまでT-3、T-7と2世代に渡ってスバル(旧・富士重工業)製の機体が採用されてきましたが、今回スバルは機体の開発には参加せず、スイス製のPC-7MKXのライセンス生産を提案していたんですね。
他に兼松がアメリカ製(原型はスイス製)のT-6、第百商事がトルコ製のHURKUSを提案していて、結果的にT-6が採用されたということですか。
T-6はアメリカ海軍・空軍が採用しているベストセラー機ですし、信頼性・性能共に申し分ないと思います。
またスバル側も、航空自衛隊向けの少数需要では大した利益が見込めないので、今回は機体の開発を行わなかったんでしょうね、本業の自動車事業に専念したいということでしょう。
 コンバット猫丸
コンバット猫丸  2024/11/29(Fri) 19:14 No.171
2024/11/29(Fri) 19:14 No.171
 航空自衛隊の初等練習機はこれまでT-3、T-7と2世代に渡ってスバル(旧・富士重工業)製の機体が採用されてきましたが、今回スバルは機体の開発には参加せず、スイス製のPC-7MKXのライセンス生産を提案していたんですね。
航空自衛隊の初等練習機はこれまでT-3、T-7と2世代に渡ってスバル(旧・富士重工業)製の機体が採用されてきましたが、今回スバルは機体の開発には参加せず、スイス製のPC-7MKXのライセンス生産を提案していたんですね。他に兼松がアメリカ製(原型はスイス製)のT-6、第百商事がトルコ製のHURKUSを提案していて、結果的にT-6が採用されたということですか。
T-6はアメリカ海軍・空軍が採用しているベストセラー機ですし、信頼性・性能共に申し分ないと思います。
またスバル側も、航空自衛隊向けの少数需要では大した利益が見込めないので、今回は機体の開発を行わなかったんでしょうね、本業の自動車事業に専念したいということでしょう。
 コンバット猫丸
コンバット猫丸  2024/11/29(Fri) 19:14 No.171
2024/11/29(Fri) 19:14 No.171
北朝鮮の新型戦車の近代改修
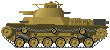 North Korea unveils new main battle tank
North Korea unveils new main battle tank
https://defence-blog.com/north-korea-unveils-new-main-battle-tank/
北朝鮮の新型戦車M2020の近代改修のモックアップ?が公開されていました。陸自の10式の近代改修も始まったので、同様の改修が行われるのではないでしょうか。
Re: 北朝鮮の新型戦車の近代改修
 M2020戦車を初めて見た時は、北朝鮮がこれだけ先進的な外観のMBTを開発したことに驚きましたが、今回公開されたモックアップはさらなる改良が施されているようですね。
M2020戦車を初めて見た時は、北朝鮮がこれだけ先進的な外観のMBTを開発したことに驚きましたが、今回公開されたモックアップはさらなる改良が施されているようですね。
従来の北朝鮮製MBTは、旧ソ連製のT-62戦車をベースに独自の改良を施したものでしたが、M2020戦車はほとんど新規設計で砲塔はアメリカのM1戦車、車体はロシアのT-14戦車に酷似してますね。
車体と砲塔前面の装甲は複合装甲で、車体各部をERA(爆発反応装甲)のブロックで覆っており、さらにAPS(アクティブ防御システム)も装備しているようです。
北朝鮮が独力でこれだけ先進的なMBTを開発するのは難しいと思われるので、おそらくロシアによる積極的な技術支援を受けたのではないでしょうか。
これは韓国も内心穏やかではないでしょうね。
 コンバット猫丸
コンバット猫丸  2024/11/25(Mon) 10:34 No.169
2024/11/25(Mon) 10:34 No.169
 M2020戦車を初めて見た時は、北朝鮮がこれだけ先進的な外観のMBTを開発したことに驚きましたが、今回公開されたモックアップはさらなる改良が施されているようですね。
M2020戦車を初めて見た時は、北朝鮮がこれだけ先進的な外観のMBTを開発したことに驚きましたが、今回公開されたモックアップはさらなる改良が施されているようですね。従来の北朝鮮製MBTは、旧ソ連製のT-62戦車をベースに独自の改良を施したものでしたが、M2020戦車はほとんど新規設計で砲塔はアメリカのM1戦車、車体はロシアのT-14戦車に酷似してますね。
車体と砲塔前面の装甲は複合装甲で、車体各部をERA(爆発反応装甲)のブロックで覆っており、さらにAPS(アクティブ防御システム)も装備しているようです。
北朝鮮が独力でこれだけ先進的なMBTを開発するのは難しいと思われるので、おそらくロシアによる積極的な技術支援を受けたのではないでしょうか。
これは韓国も内心穏やかではないでしょうね。
 コンバット猫丸
コンバット猫丸  2024/11/25(Mon) 10:34 No.169
2024/11/25(Mon) 10:34 No.169
 タンコスキー
タンコスキー 